沢風大過(たくふうたいか)本卦
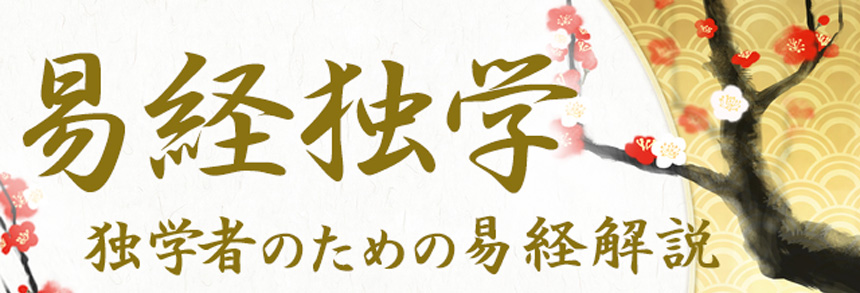
沢風大過 本卦
たくふうたいか ほんか
- 沢風大過 本卦 下へスクロール
- 沢風大過 初爻(しょこう)はこちら
- 沢風大過 二爻(にこう)はこちら
- 沢風大過 三爻(さんこう)はこちら
- 沢風大過 四爻(よんこう)はこちら
- 沢風大過 五爻(ごこう)はこちら
- 沢風大過 上爻(じょうこう)はこちら
沢風大過 本卦の解説
━ ━
━━━
━━━主爻
━━━
━━━
━ ━
〈卦辞〉
「大過は棟撓む。往く攸あるに利ろし。亨る」
〈読み方〉
たいかは むなぎ たわむ。いくところ あるに よろし。とおる。
〈説明の要点〉
ひとつ前の山雷頤の卦を裏返しにしたのが、この沢風大過です。
大過という卦は、文字の示すとおり「大いなるものの過ぎたる」卦ですし、また「大いに過ぎたる」卦でもあります。
巽下・兌上がなぜ大過か?と言えば、色々ありますが、まず表面的な爻の陰陽の上からだけ見ても、四陽二陰で、しかもその陽が中央を占領していて強すぎます。
そういった所に、この名の根拠を見て良いでしょう。
では、四対二よりも、一陰五陽のほうが開きが大きく、それこそ大過になるのではとも思いますが、一つしかないというものは貴ぶという心理を易では重要視しています。
ですから、一つしかないものは皆がそれを求めるので大過の意味を持ちません。
この卦と対照的なのは雷山小過です。
雷山小過は、陽が二つで、陰が四つです。
ですから「小なるもの過ぎたる」卦であり「小さきに過ぎる」卦とも言えます。
ちょうど大過と反対です。
大過と小過…この両者を見てすぐに気が付くことは、両方とも陰でもって陽を挟み包んでいます。
こういう形の卦は、この二つ以外には求めることができません。
そして陰陽の勢力の均衡を見て、陽の過ぎたるを大過、陰の過ぎたるを小過と見做しているのです。
棟というのは、屋根を支える大きな横木です。
これは屋根の中心にあります。
上下二陰の間に四陽爻が横たわっているのを棟にかたどったわけです。
ところが、この卦の棟の支えになっている両端は、初爻と上爻のような陰の弱いものなので、二爻から五爻までの陽の重さに堪えかねている。
屋根の重みを良く支え切れずに棟がたわんでいるということは、今にもその建物が覆ろうという危険にさらされているところです。
その危険というのも、棟上の重さが大に過ぎているからです。
このように大過は非常・危険の時です。
危険だと言って、そのまま静観していれば、やがて覆滅が襲ってくるだけです。
なんとかして、これを救わなくてはなりません。
「往く攸あるに利ろし」とは、そういった意味です。
(加藤大岳述 易学大講座 現代語要訳)




