沢水困(たくすいこん)本卦
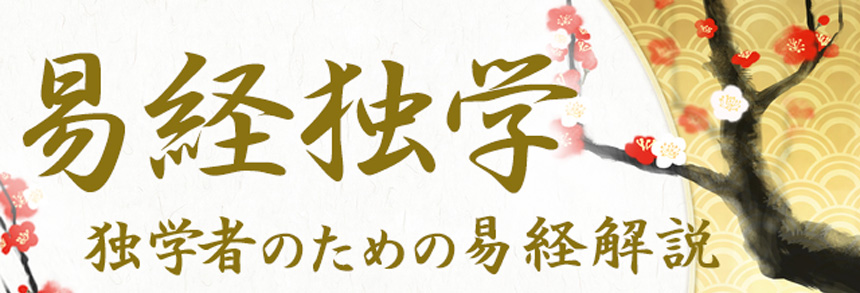
沢水困 本卦
たくすいこん ほんか
- 沢水困 本卦 下へスクロール
- 沢水困 初爻(しょこう)はこちら
- 沢水困 二爻(にこう)はこちら
- 沢水困 三爻(さんこう)はこちら
- 沢水困 四爻(よんこう)はこちら
- 沢水困 五爻(ごこう)はこちら
- 沢水困 上爻(じょうこう)はこちら
沢水困 本卦の解説
━ ━
━━━
━━━
━ ━
━━━主爻
━ ━
〈卦辞〉
「困は、亨る。貞し。大人は吉にして咎なし。言あるも信ぜられず」
〈読み方〉
こんは、とおる。ただし。たいじんは きちにして とがなし。ことあるも しんぜられず。
〈説明の要点〉
困は「こまる」と読むように、苦しみ・難み・窮することで、これらの意を重ねて、困苦・困難・困窮というような言葉があります。
そして同じく「くるしみ・なやむ」内容の屯・蹇・重坎と合わせ、これを易の四難卦としています。
では、この三陰三陽からなる「沢水困」は、どんな困苦なのでしょう。
まず、外卦兌の沢の上に在るべき坎の水が、下に漏れて来てしまって、水の涸れている状態です。
涸渇の苦難です。
あるべきところに、あるものが無いというのは、それ自体が一つの「困」です。
それはまた、無い所に必要とするものを有るようにしようとする努力と、それが叶わない苦しみを結果とすることにもなり、それが窮するの「困」です。
それから、坎の水はあるが、それが在るべきでない兌沢の外にあるということは、物が正しく配されていない、適当に行きわたっていないという「困」も生じさせています。
そして中爻である、二爻も五爻も陽(君子)でありながら、みな陰(小人)に覆われ、君子の道が表れないという「困」の世界も考えています。
「困は、亨る」の亨るとは、発展成功するというのではなく、「窮通」することです。
また「貞し」とは、その困しさに節を曲げ、遯れて難を免れるのではなく、あくまでも正しい所を守り通すのだとすることです。
それは、大人にして初めてできることだというのが「大人は吉にして咎なし」です。
そして「言あり」というのは、「言いたい事がある」というのと「言葉を用いることが多い」という両方の意味を併せもっておりますが、これは外卦兌の象です。
同じ外卦の兌から、君子が困中にあっても悦びを失わないことと、小人は困に際して口舌の意味を取っています。
「信」というのは、もちろん坎の孚です。
ところが、その坎は兌の中から漏れうせてしまっているのが困なのですから「言あるも信ぜられず」なわけです。
(加藤大岳述 易学大講座 現代語要訳)




